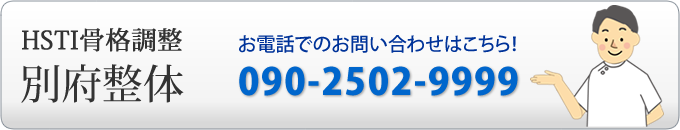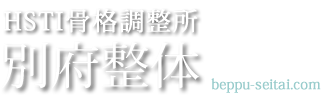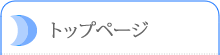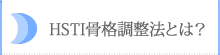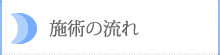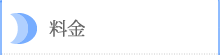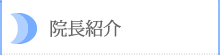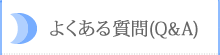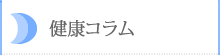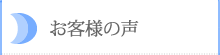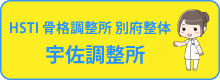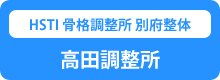健康コラム ~「かぜ」について ~
良質のたんぱく質とビタミンA・Cがかぜの特効薬
かぜは、ウイルスの感染によっておこることがほとんどです。ウイルスが体内に入りこんだ時、疲労・睡眠不足・栄養不足・寒さなどで、体力が落ち、抵抗力がない場合に発病します。 初期の症状は、くしゃみ・鼻汁・さむけ・発熱・頭痛などです。この段階で適切な手当をして、早めに治してしまいましょう。 手当の基本は、栄養をとること、あたたかくして休むことです。食欲がないとき、胃腸が弱っているときは、消化がよく、食べやすいものを工夫します。 からだをあたためる食べもの、細胞の抵抗力を高めるビタミンA・Cを含むものを積極的にとりましょう。
卵 ~消化がよく、栄養豊富
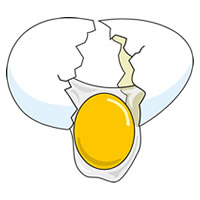
卵は、たんぱく質などバランスのよい高栄養素がとれ、汗を出して熱を下げます。白身には、のどを潤し、せきを鎮める作用もあります。卵酒は、かぜのひきはじめの微熱によく効きます。ただし、高い熱にはかえって悪化をまねくことがあるので注意しましょう。また卵のアレルギーのある人、酒の弱い人にはむきません。
【レシピ】卵酒の作り方
| 材料 (1杯分) |
・卵・・・・・・・・・・・ 1個
・日本酒・・・・・・・ 180ml(カップ1弱) ・しょうが・・・・・ 1かけ ・砂糖・・・・・・・・・ 適量 |
|---|---|
| 作り方 | ①なべに日本酒を入れ、沸騰させる。沸騰するとふきこぼれやすいので気をつける
②沸騰したら、卵を割り入れ、すぐに火をとめ、はしでかきまぜる ③しょうがをすりおろして入れる ④好みで砂糖を入れ、熱いうちに飲みましょう |
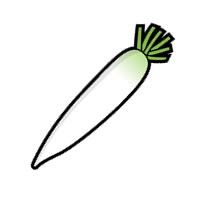
ジアスターゼなど消化酵素が豊富で、消化促進や胃を強くする作用が良く知られていますが、せきどめやたんをだしやすくするはたらきもあります。 せき、たんやのどの痛み、のどの渇きには、だいこん湯がおすすめです。コップ1/4くらいのだいこんおろしに、おろししょうがを少々加え、熱湯を注いであたたかいうちに飲みます。ハチミツで甘くしたり、レモンの絞り汁の酸味で飲みやすくしてもよいでしょう。
にら ~胃腸が弱ったときに
にらの強いにおいのもとになるアリルという物質が、自律神経を刺激し、冷えた胃腸や内臓の調子を整えます。ビタミンA・B・C・カルシウム・カリウム・鉄も多く、かぜのときの栄養補給に最適です。血液循環をよくするはたらきもあります。
にら粥かにら雑炊にして食べると、体があたたまるうえ、体の冷えからくる胃腸の痛みにも効果があります。ただし、アレルギー体質の人、下痢をしやすい人は、食べ過ぎないよう注意が必要です。
【レシピ】にら粥の作り方
| 作り方 | ①塩味でうすく味付けした白粥か、みそ味のお粥を炊く ②火を止める直前に、きざんだにら70~100g(1/2束)を入れて蒸らす |
|---|
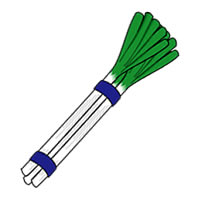
ねぎの白い部分は、漢方では葱白(そうはく)といい、汗を出して熱を下げ、体をあたためます。ただし、熱があって、すでに汗をかいている場合には使えません。
ねぎの白いところをみじん切りにしてみそをまぜ、熱湯を注いだスープや、しょうがのしぼり汁を加えたお粥やスープを飲みます。
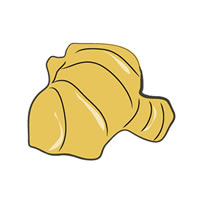
かぜの頭痛、せき、鼻づまり、冷えなどに効果があります。辛み成分には殺菌力もあります。せき、たんには、しょうが汁にハチミツを入れてあたためたしょうが湯を飲みます。親指大ぐらいのしょうがおろし汁に熱湯を注ぎ、ハチミツは好みにあわせて入れます。
うめ ~解熱効果がある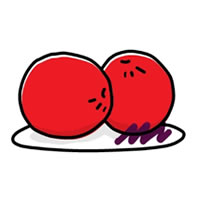
うめぼしの黒焼きは、せきどめや解熱に効果があります。黒焼きは、うめぼしを焼き網かフライパンで真っ黒になるまで弱火であぶります。黒焼きのうめぼし2個を器に入れて黒砂糖5gを加え、カップ半分くらいの熱湯をさして、うわずみをあたたかいうちに飲みます。
おもしろ栄養学 ~ビタミンCは、なぜかぜに効く?
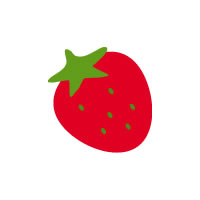
ビタミンCには、ウイルスの感染を防ごうとする体のはたらきを強める作用があります。またウイルスそのものを殺す力や、寒さに対する抵抗力をつけるはたらきもあります。
さらに、ウイルスが破壊した細胞や組織回復したり、薬の副作用の防止にも役立つので、かぜの予防はもとより、ひきはじめから回復期まで効果をあらわします。
かぜをひいて熱が出ると、体内のビタミンCが減ります。特に、白血球に含まれるビタミンCの濃度が減少します。そこで積極的にビタミンCをとる必要があるのです。
ビタミンCは、柑橘類、パイナップル、いちごなどのくだものや、野菜ではパセリやピーマンなどの緑黄色野菜に多く含まれます。加熱すると破壊されるので、生のジュースにして飲むのが、手軽で効果的です。