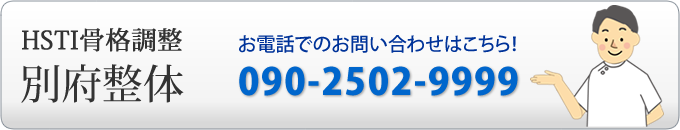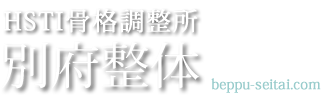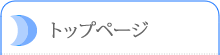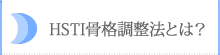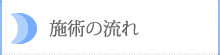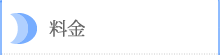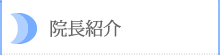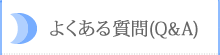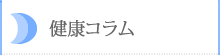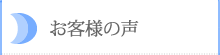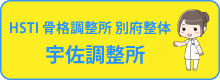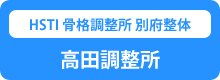健康コラム ~「めまい」について ~
今月は「めまい」についてです。
めまいの原因はさまざまだが、とりあえず安静が大切。

めまいには、急に立ち上がったときにクラッとして、目の前が暗くなる立ちくらみ程度の軽いものから、突然まわりの景色がぐるぐる回ったりするように感じるものまでいろいろあります。
原因は、おもに『内耳など体の平衡感覚を支配する部分に病気や異常があるためにおこるもの』『血圧の異常で脳へ送られる血液量が減少するためにおこるもの』の2つに分けることができます。
内耳などの異常が原因となる場合は、回転性のめまいがおこります。代表的なのがメニエール病です。最近この病気にかかる人が急増しており、心身の疲労が大きく原因していると考えられています。
脳への血液量が減っておこるめまいは、日常よくみられます。特に病的な原因がなくおこることが少なくありません。たとえば、睡眠不足や過労、または体質的に低血圧ぎみだったり、貧血をおこしやすい人が多いようです。それ以外では、更年期障害や自律神経失調症などによってもおこります。
どちらにしても、とりあえずは安静を保つことが大切です。また、日ごろからビタミンやカルシウムを十分とるように心がけてください。
めまいから考えられるおもな病気
[ぐるぐる回る]
急性中耳炎
耳が激しく痛み、耳だれがある。高熱、頭痛、耳鳴りがし、耳のふさがった感じを伴う
メニエール病
ふだんはなんともないが、症状が出ると耳鳴りや難聴を伴う。めまいは激しい。嘔吐、頭痛が繰り返しある。
内耳炎
片側の耳がつまった感じがする。耳鳴り、難聴、吐き気、嘔吐、めまいなどがある。
耳性帯状疱疹
耳のまわりに赤い小さな水泡が帯状にでき、激痛がする。聴神経がおかされると、難聴やめまい伴う。
[ふらふらしためまい感がある]
脳貧血
顔色が青くなり、手足は冷たくなる。冷や汗、生あくび、吐き気もある。目の前が真っ暗になって倒れることも。
低血圧症
立ちくらみのほか、頭痛、肩こり、耳鳴り、めまい、動悸、息切れなどがある。また、だるく疲れやすい。
起立性低血圧症
動悸がして気分が悪い、急に立ち上がったり長時間立ち続けたときにおこる
高血圧症・変形性頚椎症
頭痛、頭重、耳鳴り、肩こり、動悸がする。急に血圧が上がった場合におこる。
頭痛にも効くぎんなんの粉末
ぎんなんには、たんぱく質やビタミン、鉄などの栄養分が豊富に含まれており、すぐれた強壮効果があります。このぎんなんと、鎮静作用のあるナツメをいっしょに用いると、めまいによく効きます。まず、ぎんなんを粉末にし、これをナツメの煎じ汁で飲みます。これは頭痛にも効果があります。
【ぎんなん粉末】の作り方
| 作り方 | ①ナツメは天日で干す。そして蒸したあと、もう一度天日干しにする。これを1日量5~7g煎じる。 ②ぎんなんをいり、すり鉢に入れて粉末にする ③ナツメの煎じ汁といっしょに②を飲む |
|---|
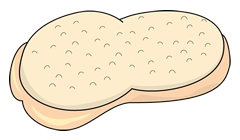
鶏肉には、虚弱体質や低血圧症、月経不順などが原因でおこるめまいに効果があります。 漢方では、めまいは水分代謝がわるくなるとおこるものと捉えています。鶏肉はこの水分代謝をよくするはたらきがあります。鶏肉に、血を補う作用のある生薬のトウキとセンキュウ〔漢方薬局で買える〕をあわせていっしょに蒸したものを食べるとよいでしょう。
【鶏肉の蒸しもの】の作り方
| 材料 | 鶏肉・・・・・・・・・・100g トウキ・・・・・・・・・15g(大さじ4) センキュウ・・・・・・・ 6g(大さじ1弱) しょうゆ・・・・・・・・適量 |
|---|---|
| 作り方 | ①鶏肉は一口大に切る ②トウキとセンキュウは小さく砕き、鶏肉とあわせて、小さなボウルか小鉢に入れる ③蒸し器に②を器ごと入れ、弱火で30分ほど蒸す ④しょうゆをつけて食べる |

サフランには、すぐれた鎮静作用があるため、めまいや頭痛によく効きます。薬効があるのは、花弁のあいだから伸びている雌しべです。これは市販されていますが、にせものが多いので購入するときは注意が必要です。めまいがおきたら、サフラン約10本を熱湯100mlの中に入れ、お湯の色がダイダイ色に染まってから、お茶のように服用します。ただし妊婦は、流産の危険があるので服用してはいけません。
なるほどゼミナール ~めまいの手当~
めまいがおきない姿勢になり、安静にしましょう!
- 横になり、頭を低くするなど、めまいがおきないような頭の位置をみつける。しばらくその位置で安静にする。
- 直射日光があたらないようにして休む。枕は使わず、からだをあたたかくするのがポイント
- 吐き気があったり、吐いてしまったときは胃を冷やす。体は横たわったまま、首は横に向けて吐きやすい状態にする。
- 歩行中、めまいがおきたら、立ち止まってその場にうずくまる。または何かによりかかって回復を待つのがよい
参照:主婦と生活社「食べて治す医学大辞典」